導入事例
【防災×教育研修×VR】臨場感ある体験で防災意識を向上|東京都 合同VR訓練 導入事例

災害はいつ起きるかわかりません。実際に経験していない人に、その怖さや備えの必要性を伝えるのは、簡単ではありません。2023年、東京都様と共同でアルファコードが開発した「みんなで防災体験VR」は、防災意識を高めるための革新的な取り組みとして注目されました。災害時の行動をリアルに体験できるこの防災VRプログラムは、従来の防災教育における課題を克服し、防災への意識や行動を見直す、きっかけとなった取り組みです。
サマリー
・概要: 東京都と共同で開発した防災VRコンテンツで、地震・水害・火山噴火の3つの災害シナリオを体験可能。
・導入前の課題: 従来の防災教育では、実際の災害時に適切な行動を取るためのリアルな体験が不足していた。
・導入後の効果: 参加者の約9割以上が防災意識を向上させ、災害時の行動が変わると回答。
従来の防災教育の限界と課題
防災教育では、地図やテキスト、ビデオを使った学習が主流ですが、これらは知識の提供には適していますが、災害時に即した行動を想定し、適切に対応するための感覚を養うには課題がありました。特に、経験のない若年層や一般住民にとって、災害の危険性を具体的に体感できないため、実際の行動変容につながりにくいという声がありました。これが今回の防災VR開発の背景となっています。
「体験」による意識改革:防災VR体験の効果
2023年に東京都が実施した「TOKYO強靭化プロジェクト」では、VR技術を活用して地震・水害・火山噴火の3つの災害シナリオを体験できる防災VRコンテンツを開発しました。この体験型防災教育では、参加者がVRを通じて「自助」「共助」「公助」の重要性を学び、防災意識を高めることができました。
防災VRの特長:
- 臨場感: 実際の災害に近い状況をリアルに再現し、危険を「自分ごと」として体感。
- 行動変容: 災害時の適切な行動を事前にシミュレーションすることで、防災スキルを向上。
- 共同体験: 家族や同僚と共に体験することで、コミュニティ全体の防災意識を高める。
防災VRの最大の特徴は、知識を「体験」に変えること。
災害を“自分ごと”として感じられることで、行動の意識まで変わっていきます。
参加者は災害時にどう行動すべきかを体験し、その結果として防災意識が向上し、行動変容が促されました。
「VRider COMMS」について見る→インターネット不要のメタバース「VRider COMMS」
防災VRの導入事例と成果
2023年に東京都が主催した「TOKYO強靭化プロジェクト」で運用されたこのコンテンツは、9割以上の参加者が「防災意識が変わった」「行動が変わった」と回答するなど、非常に高い効果が確認されています。
防災VR参加者の声:
- 「水害や地震のリアルな体験が、防災計画を見直すきっかけになった」
- 「コミュニティ全体で共有体験をすることで、有事の際の協力意識が芽生えた」
防災VR関連記事:一般社団法人 自治体DX推進協議会記事「「体験」が防災意識と有事の行動を変える 防災・災害対応におけるXR技術の可能性」

東京都の関東大震災100年イベントでの防災VR体験の様子(出典:同上記事)

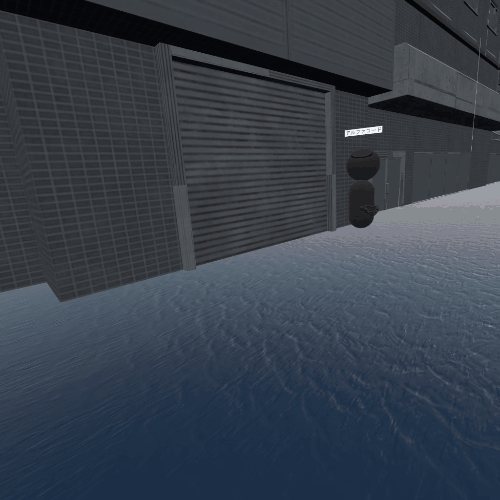
▲豪雨により水面が迫ってくる様子が臨場感とともに体験できる。
防災体験の未来とXR技術の可能性
今後、XR技術は災害対応訓練だけでなく、教育や訓練全般にわたる活用が期待されています。AIとの連携によるパーソナライズされた防災シミュレーションや、地域ごとの特性に合わせたカスタマイズが可能となれば、住民一人ひとりの防災意識向上に大きく貢献するでしょう。
アルファコードの「みんなで防災体験VR」は、こうした未来を先取りした取り組みとして、これからの防災教育の“あたりまえ”になっていくかもしれません。現場での導入を検討される方は、ぜひアルファコードのXRソリューションをご覧ください。
関連記事:「アルファコード、東京都主催「先端技術を活用した、都民の防災意識向上に資するコンテンツの開発」ピッチコンテスト優勝」
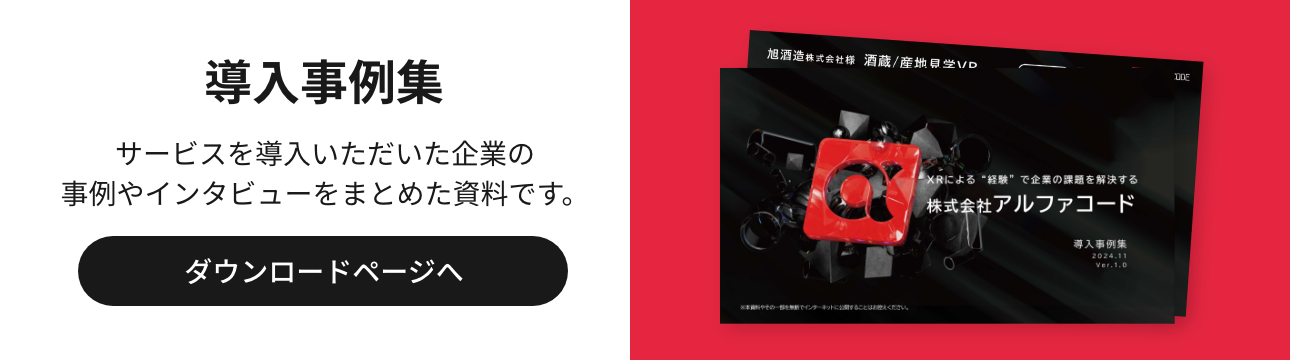

お問い合わせ CONTACT


資料請求 DOWNLOAD








